「もし突然、収入がなくなったら・・・」そんなときに、家計を守ってくれるのが「生活防衛費」です。
- 生活防衛費は100万円あれば十分?
- どこに預ければいいの?
- そもそも本当に必要なの?
そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、
- 生活防衛費の意味と役割
- 必要額の目安と計算方法
- 効率的な貯め方とおすすめの口座
- 毎月の積立額と他の貯金とのバランス
- 生活防衛費のよくある質問
などを紹介します。
 すず
すず生活防衛費を貯めておくことで、将来への不安を減らすことができるので、ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです🥰
生活防衛費とは?
病気やケガ、突然の失業などで一時的に収入が途絶えたときに備えるお金のこと。
「万が一、働けなくなったとしても、最低限の生活費をまかなえる安心資金」と考えるとイメージしやすいです。
例えば、生活防衛費を貯めておくことで、このようなメリットがあります。
- 急な出費にも慌てずに対応できる
- 不要な保険に入らずに済む保険の見直しにもつながる
- 精神的にも安心でき、暮らしの安定感が増す
「貯金がある」というだけで、不安が和らぎ、心にゆとりが生まれます。
生活防衛費はいくら必要?目安と計算方法
生活防衛費の目安は「毎月の生活費をベースに計算する」のがポイント💡
ここでは、必要額の目安と、実際の計算方法を紹介します。
必要額の目安は「生活費の3~6ヶ月分」
一般的に、生活防衛費の目安は、
「毎月の生活費の3~6ヶ月分」と言われています。
その理由は、失業した場合の転職活動や、病気・ケガからの体調回復に必要な期間として、3ヶ月~6ヶ月くらいを見ておくと安心だからだそうです。
ただし、必要な期間は人それぞれ。
「自分だったら、何か月で生活を立て直せるかな?」と想像し、自分にとって「安心できる金額」を考えてみてくさい🥰



我が家は、私が専業主婦なこともあり、少しゆとりをもった「6ヶ月分」の生活防衛費を準備しました💰
人によっては、より安心のために「6ヶ月~12ヶ月分」まで準備している方もいるそうです。
まずは「最低3ヶ月分」を目標に、余裕があれば「6~12ヶ月分」を目指すと安心です🌷
生活防衛費の計算方法
生活防衛費の計算方法はシンプルです👇🏻
生活防衛費=月の支出×3~6ヶ月分
例えば、毎月の支出が20万円なら・・・
- 20万円×3ヶ月=60万円
- 20万円×6ヶ月=120万円
この範囲が、自分に必要な生活防衛費の目安となります。
毎月の支出をベースに計算することで、自分にとって必要な金額がわかるようになります。



金額が見えると、貯めるモチベーションもアップ✨
▼まだ「自分の支出を把握していない」という方は、こちらの記事も読んでみてください👇🏻


生活防衛費のおすすめの貯め方
「必要額は分かったけれど、実際どうやって貯めればいいの?」
ここからは、生活防衛費を効率よく貯めるための方法を紹介します。
すぐに実践できる2つの貯め方を押さえておけば、無理なくコツコツ準備することができます🥰
① 先取貯金でコツコツ貯める
給料が入ったら、まず生活防衛費用の貯金口座に移す「先取貯金」がおすすめ。
「残ったら貯める」のではなく「先に貯める」のがポイントです💡
▼先取貯金についてはこちらにまとめています。


② ボーナスから積み立てる
毎月の先取貯金に加えて、ボーナスを活用するとまとまったお金を貯められるので早めに貯めることができます。
▼ボーナスの管理方法についてはこちらにまとめています。


生活防衛費は、毎月コツコツ積み立てながら、ボーナスでまとまった額を貯めるのが効率的。
少しずつでも貯めていくことで、安心感が増しモチベーションUPにもつながります🥰
生活防衛費はどこに預ける?
生活防衛費は「いざという時にすぐ使える」ことが一番大事。
せっかく準備しても、必要な時に引き出せなければ意味がないので、
いつでも引き出せて、安全性が高い「普通預金」に預けるのがおすすめです。
中には「投資や定期預金などで少しでも増やしたい」と思う方もいるかもしれませんが、
生活防衛費は「増やすお金ではなく、守るお金」。
投資や長期の定期預金に入れてしまうと、急に必要になったときに、引き出せず困ってしまう可能性があります。
どうしても「少しでも増やしたい」場合は、普通預金中でも金利が高めのネット銀行やあおぞら銀行などを選ぶのも一つの方法です。
毎月どのぐらい貯めればいい?生活防衛費と他の貯金のバランス
生活防衛費は「2~3年で貯め切る」のがおすすめ。
その理由は、生活防衛費だけに全力を注いでしまうと、旅行費やレジャー費、教育資金、老後資金などの、他の大事な貯金が後回しになってしまうからです。
例えば、毎月の生活費が20万円で生活防衛費を「6ヶ月=120万円」貯めたい場合、毎月の積立額はこのようになります。
| 貯める期間 | 毎月の積立額 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1年 | 10万円 | 早く安心できるが負担が大きい |
| 2年 | 5万円 | バランスがよく無理なく続けられる |
| 3年 | 3.4万円 | 負担は少ないが安心できるまで時間がかかる |
「他の貯金もあるから、毎月5万円を生活防衛費に回すのは厳しい・・・💭」という方も大丈夫✨
例えば、毎月3万円は生活防衛費、2万円は他の貯金、残りはボーナスで補填するなど工夫することで、無理なくバランスよく貯めることができます。
生活防衛費が目標額まで貯まったら、あとは他の貯金を優先できるので、まずは2~3年を目安に「生活防衛費を優先して貯め切る」ことをおすすめします。
まとめ│生活防衛費があるだけで安心につながる
病気やケガ、突然の失業など「もしも」のときに家計を守ってくれるのが、生活防衛費です。
この記事で紹介したポイントをおさらいすると、
- 生活防衛費は、いざという時に生活を守るためのお金
- 必要額の目安は「生活費の3~6ヶ月分」
- 貯め方は「先取貯金+ボーナスで補填」が効率的
- 預ける場所は「普通預金」(引き出しやすさを最優先)
- 目標は、2~3年で貯め切るのがおすすめ
生活防衛費は「増やすお金」ではなく「守るお金」。
一度準備できれば、それだけで心に大きな安心が生まれ、他の貯金にも集中できるようになります。
まだ、準備していない方も、まずは「1ヶ月」からでもいいのでスタートしてみてください。
小さな一歩が、将来の大きな安心につながります🥰
よくある質問(Q&A)
借金やローンがある場合でも、生活防衛費を優先すべき?
高金利で借入がある場合は、まず返済を優先することがおすすめです。
利息の負担が大きいため、早めに返した方が家計的にプラスになります。
ただし、生活防衛費がまったくないのも不安要素。返済を優先しつつ、同時に少しずつ生活防衛費を貯めていくのが安心です。
投資信託や株式で備えるのはだめ?
基本的にはおすすめしません。
投資商品は値動きがあるため、必要な時に元本割れしている可能性があるからです。
生活防衛費は「安全・すぐに使える」ことが大切。
まずは普通預金しっかり確保し、投資は生活防衛費が貯まったあとに始めるのが安心です。
子供がいる家庭の場合でも3~6ヶ月分で良いの?
子育て世帯は支出が増えやすく、突然の出費も多いもの。
そのため、生活防衛費も多めに(6~12ヶ月分を目安に)準備しておくと安心です。
共働きの場合は、生活防衛費はいらないですか?
収入源が2つある共働きの家庭では、失業リスクが分散されます。
ただし、どちらかの収入が減る可能性はあるため、最低でも3ヶ月分の生活費は確保しておくと安心です。
生活防衛費は、100万円貯めればいい?
独身で生活費が少ない方なら、100万円でも十分だと思います。ただし、家族がいる方や住宅ローンがある方は、不足しがちなので「生活費の3~6ヶ月」を目安に、自分の暮らしにあった金額を準備するのがおすすめです。
最後まで読んで頂きありがとうございました🌷
少しでも参考になれれば嬉しいです!
もし、この記事を気に入っていただけたら、
他の「貯め体質になる暮らし」の記事もぜひ、のぞいてもらえたら嬉しいです👀✨
もし何かありましたら、
コメントやお問い合わせまでお気軽にどうぞ🌸
今日も家計管理、おつかれさまでした🌿✨


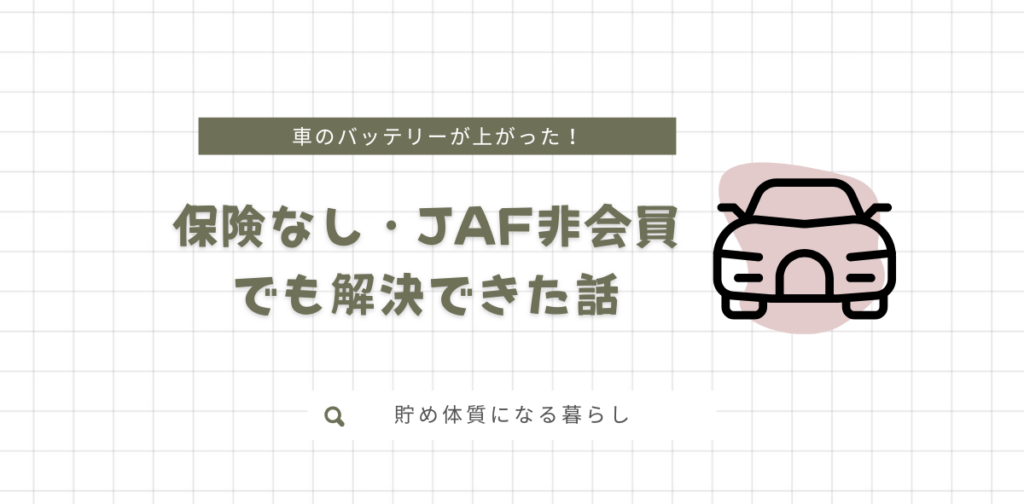




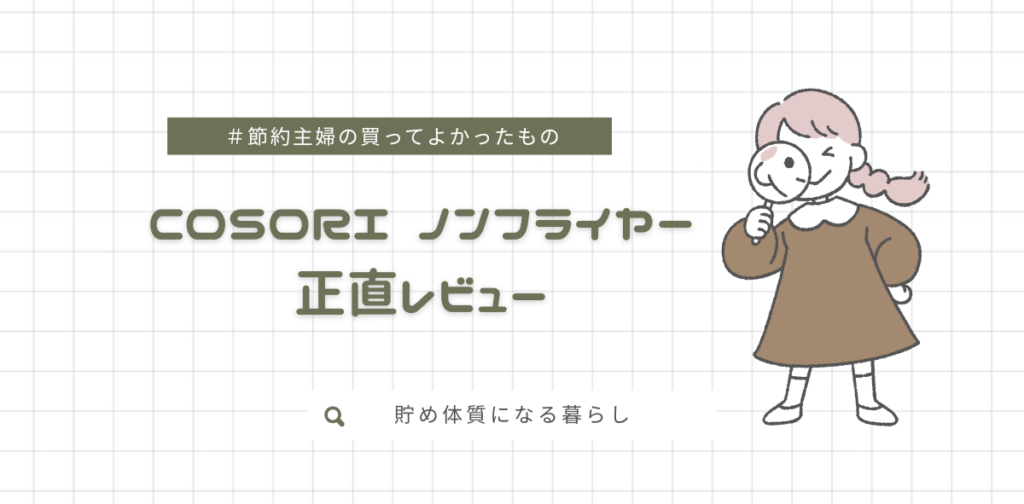
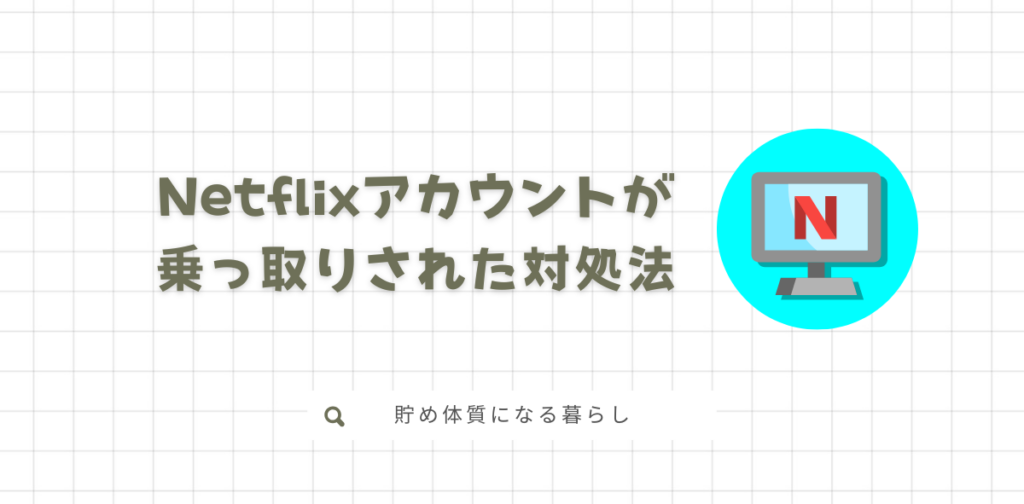




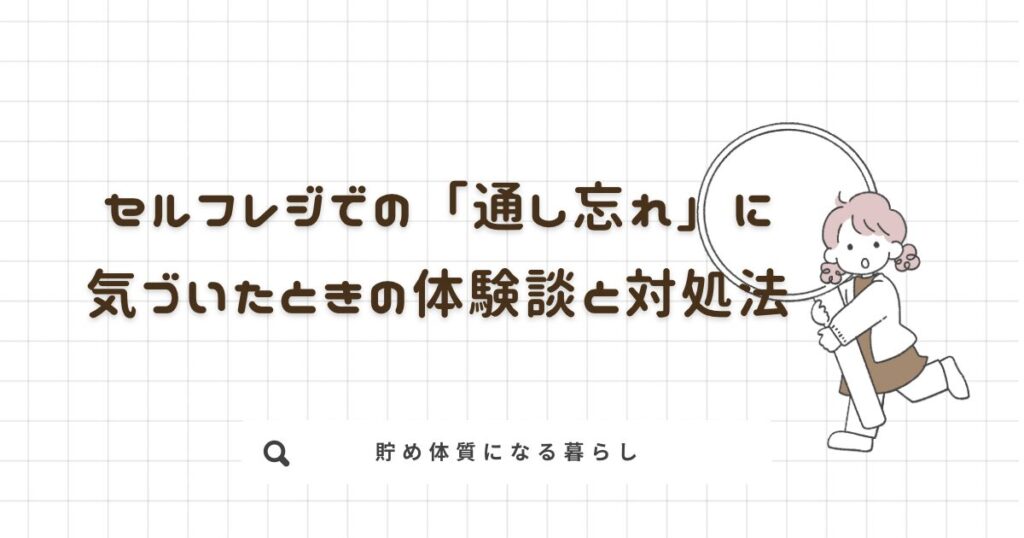
コメント