- 節約をして貯金は増えてきているのに、なんだか気持ちが満たされない
- たまのプチ贅沢にも「こんなことに使っていいのかな?」と罪悪感
- 自由に使えるお金がなくて、気づけばストレスばかり
そんな風に感じていませんか?
私も以前は「貯金のために節約!」と我慢ばかりの節約を続けていたのですが、気づけば心がヘトヘトに・・・🥲
でもある方法を取り入れてからは、貯金を崩すことなく、生活の満足度を保ったまま、気持ちよくお金を使えるようになりました。
この記事では「生活の満足度を下げずに節約するための考え方や仕組み」について紹介します。
 すず
すずお金の使い方に罪悪感を抱えている方や「節約しつつも暮らしを楽しみたい」という方の参考になれれば嬉しいです。
ストレスなく節約するコツ│自由に使えるお金の作り方
私は以前、「節約=我慢」だと思い込んでいて、貯金が増えても気持ちが満たされず、どこかモヤモヤしていました。
使いたいけど使えない・・・いわば、
「お金使えない症候群」になっていたのです。
例えば、旅行先でもちょっと高めのごはんを目の前のしても「もったいないかも・・・」と楽しめなかったり、好きなガチャガチャを見かけても「無駄遣い」と自分を止めてしまったり・・・。
でも、ずっと「使わない」選択を続けていると、心がどんどん疲れていくことに気づいたんです。
だからこそ私は、生活の満足度を下げずに節約を続けるための仕組みとして「自由に使えるお金の枠をつくる」ことを考えるようになりました。
とはいえ、最初から予算を増やすのは難しいし、そもそも余裕があるなら悩んでいないですよね・・・。
そこで始めたのが、やりくり費①の余りを「もともと使う予定のお金」と捉え直し、貯金には回さず「自由に使っていいお金」として分けて管理する方法です。
このお金は、頑張って節約して生まれた貯金に回すお金ではなく、最初から使う予定だったお金。
だからこそ、罪悪感なく、普段「無駄かな?」と思えるようなことにでも気持ちよく使うことができるのです。
この方法を取り入れてから、
- 我慢しがちなプチ贅沢も、罪悪感なく楽しめる
- 節約しながらも、心にゆとりが生まれる
- お金を使う練習にもなり「お金を使うこと=悪」という思い込みも手放せる
など、ストレスを感じすぎることなく、気持ちよく節約が続けれるようになりました。
▼お金使えない症候群から抜け出した5つの方法はこちら
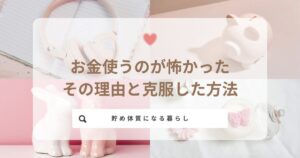
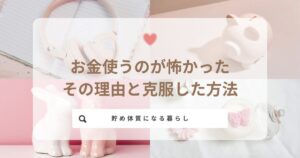
やりくり費①とは?
まず初めに、「やりくり費①ってなに?」という方のために簡単に説明します。
毎月必ずかかる生活費を予算内でやりくりする支出のこと。
例えば我が家の場合、食費・日用品・娯楽費、この3つが「やりくり費①」にあたります。
※やりくり費②(毎月ではないけど予算を決めてやりくりする支出)もありますが、こちらは余りは貯金に回すルールにしています。
▼やりくり費についてはこちらで詳しく紹介しています。


やりくり費①の余りはどうしてる?貯金しない選択で心にゆとりを
やりくり費①の余りは貯金に回さず、
「にこにこ貯金として別で管理しています。



ネーミングのセンスはご容赦ください・・・笑
「にこにこ貯金」とは、その名のとおり、
笑顔になれるために使うお金のこと。
例えば、
- 家族旅行中の外食費
- 焼肉食べ放題などの少し贅沢な外食
- 映画鑑賞
- 月の後半に予算が過ぎそうな時のピンチ費
- ガチャガチャなどのプチ娯楽費
など、「ほんとは使いたいけど、もったいないから我慢しちゃう」そんな支出も、罪悪感なく楽しめるようになります。



こういった支出が、心を整えてくれる大切な「支出」だったりしますよね🥰🌿
やりくり費①の余りを家計簿でどう管理するの?
- やりくり費①が余った場合、家計簿ではどう管理すればいいの?
- 貯金額と合わなくならない?
そんな疑問が出てくる方もいると思います。
私が実践しているのは「家計簿では予算を満額使ったことにする」という方法です。
例えば、固定費:15万円・やりくり費①:3.5万円(予算4万円)・やりくり費②:3万円の支出の場合、本来の支出合計額は21.5万円ですが、家計簿ではやりくり費①を満額しようしたことにするので、支出合計は22万円として計算します。
余った5,000円は「にこにこ貯金」へ
こうしておくことで、家計簿とのズレが生まれず管理をすることができ、余りを「自由に使えるお金」として活用することができます🌷
やりくり費①にこだわる理由│節約と満足度のバランスをとる秘訣
「なぜ、やりくり費①なの?」と感じた方もいると思います。
その理由は、やりくり費①が、日々の満足度に直結するお金だからです。
例えば、
- 食費
- 日用品
- 娯楽費
このあたりを無理に削ると、生活そのものが窮屈に感じられるようになってしまいます。
特に食費は、体調や気持ちにも直結する大切な支出。「少しでも貯金を増やしたい」と思ってここを削ると、心も体も疲れやすくなってしまいます。
だからこそ私は、やりくり費①の余りを「にこにこ貯金」として、「自由に使えるお金」として分けてることにしました。
やりくり費①の余りを「にこにこ貯金」にするメリット
この方法にはこんなメリットがあります👇🏻
- 余りを貯金に回さないから、無理な節約をせず、予算を気持ちよく使い切れる
- 「自由に使ってもいいお金」があるだけで、心にゆとりが生まれる
- 気持ちの余白ができて、節約の反動(爆発🤯)や衝動買いを防げる
「貯金もしたいけど、ちょっと贅沢もしたい」そんな気持ちを大切にできるのが、にこにこ貯金のいいとことです🥰



自分の気持ちとお金、どちらも大事にできる仕組みを、少しずつ整えていきましょう👀✨
「にこにこ貯金│おすすめのアイテムとモチベUP術
「にこにこ貯金ってどうやって管理しているの?」と思う方もいると思うので、我が家の管理方法を紹介します。
私が使っている管理アイテムはこちら👇🏻


使っているのはダイソーのコインケース
- 上段に【硬貨】、下段に【お札】が入る設計で、とっても便利!
- 使い勝手が良くて、貯金額が見える化できるのがポイント◎
さらに、私はこのコインケースを、お気に入りのお菓子の缶に入れて管理しています🍭
お気に入りの缶でモチベーションUP
「にこにこ貯金」は、ただの余りではなく、自分や家族が笑顔になれるためのお金。
なので、お気に入りのアイテムで楽しく管理することが、モチベーションにも繋がります🫶🏻!



さらに、両替したい時にも便利で、我が家ではこのコインケースを「おうちATM」とも呼んでいます🤭🏦
まとめ│「頑張らない貯金」が長続きのコツ
今回紹介した「にこにこ貯金」のように、自分に合った仕組みを作ることが、節約や貯金を無理なく続けるための、カギになります。
節約は頑張りすぎると、ダイエットと同じように、ある日突然、反動が来てしまうもの🤯
だからこそ大切なのは、
自分に合った予算の中で、無理なく・楽しく・気持ちよくお金を使うこと。
やりくり費①の余りを「にこにこ貯金」として分けておくだけで、
- 我慢しがちなプチ贅沢も罪悪感なく楽しめる
- お金を使う練習にもなり、使うことへの罪悪感が薄れる
- 心にゆとりが生まれ、自然と節約や貯金が続くようになる
そんな実感があります。



「お金=我慢」から「お金=自分を大切にする手段」へ。そんな風に感じられるきっかけになれれば嬉しいです🥰
「にこにこ貯金」のQ&A
▼やりくり費の仕組みや、貯金の習慣化についても紹介しています💌




最後まで読んで頂きありがとうございました🌷
少しでも参考になれれば嬉しいです!
もし、この記事を気に入っていただけたら、
他の「貯め体質になる暮らし」の記事もぜひ、のぞいてもらえたら嬉しいです👀✨
もし何かありましたら、
コメントやお問い合わせまでお気軽にどうぞ🌸
今日も家計管理、おつかれさまでした🌿✨


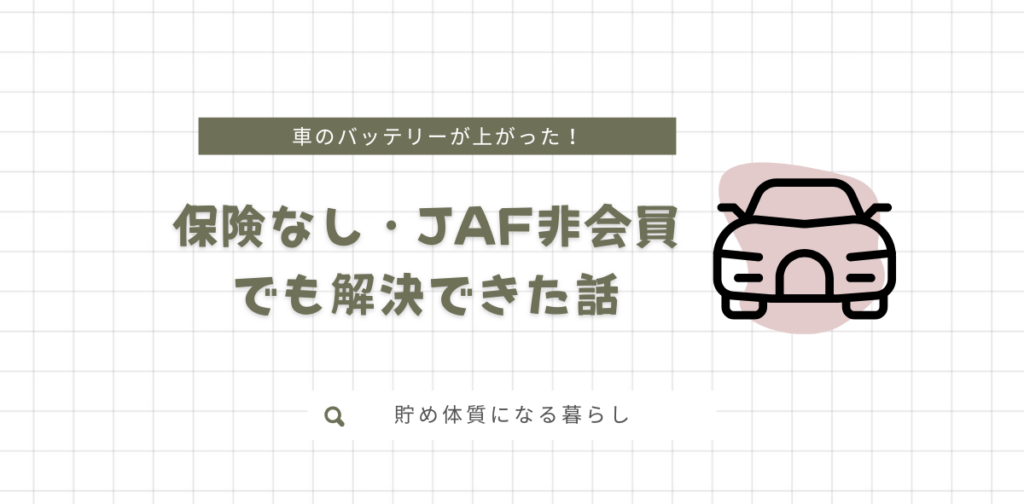




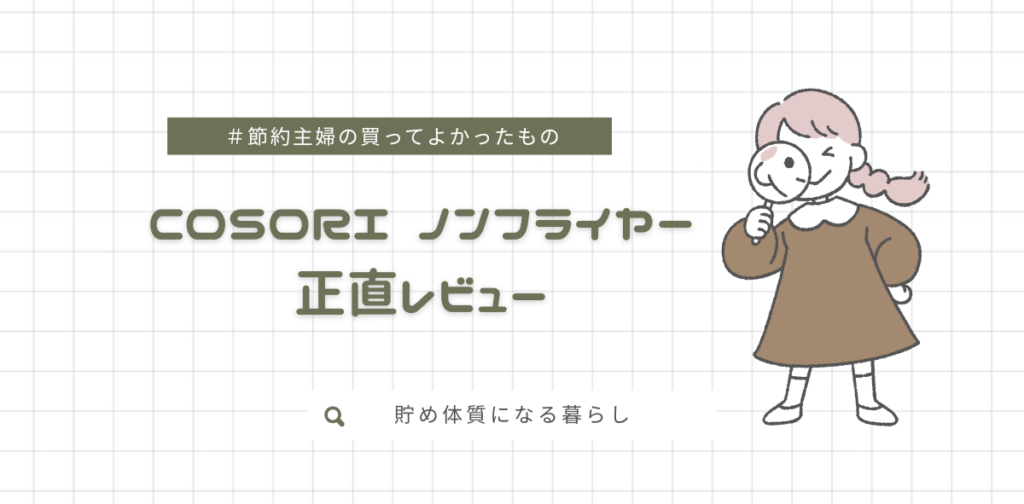
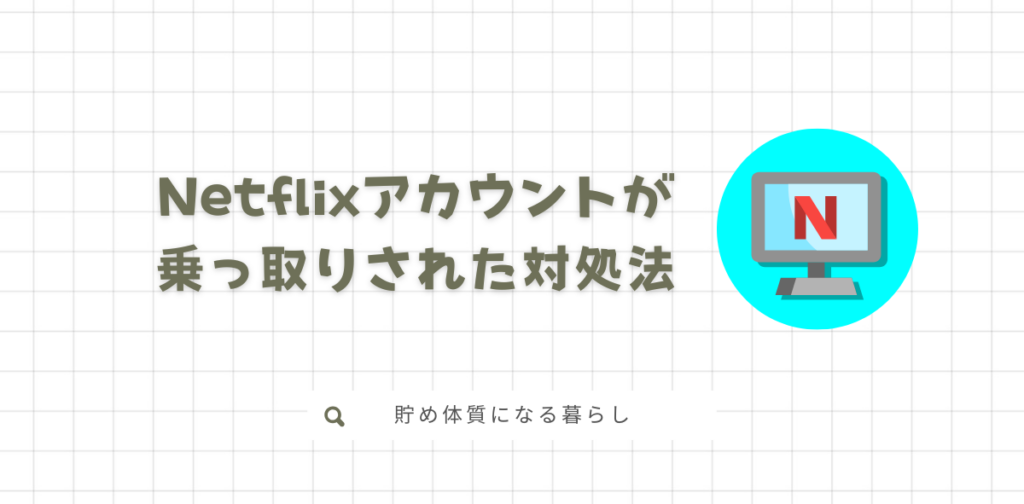




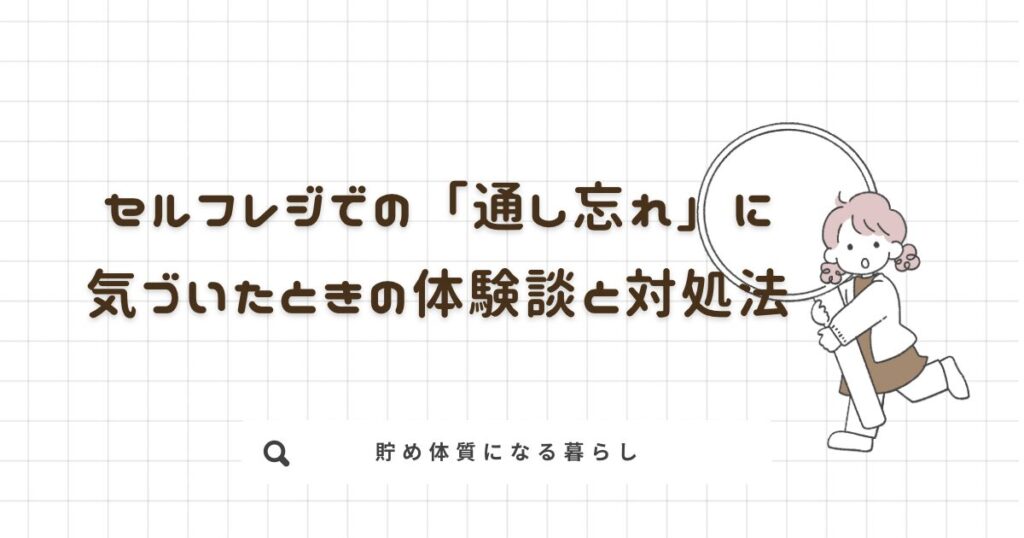
コメント