- 運転が怖くてできない
- 道に迷いやすい
- 道案内が苦手
そんな悩みを抱えている方はいませんか?
実は私もそのひとりで、免許は持っているのに怖くて運転はできず、さらに方向音痴で、道案内も苦手・・・。
「なんで自分はできないんだろう?」と長い間悩んでいました。
そんな中、先日健康診断で受けた「認知症体験テスト」をきっかけに、
もしかしてこれは空間認識能力に苦手さが関係しているのかもしれないと気づいたのです。
自分と物体との位置関係や距離を把握する力のこと。
運転や道案内だけではなく、日常生活のさまざまな場面に関わっています。
この記事では、
- 空間認識能力とは何か
- 苦手だと日常生活にどんな影響があるのか(体験談)
- 大人でもできる鍛え方
を紹介しています。
同じように悩んでいる方が、少しでも安心できるきっかけになれば嬉しいです。
この記事は空間認識能力が苦手な私の体験談をもとに書いています。専門的な診断や治療の内容ではありませんので、その点はご理解いただければ嬉しいです。
空間認識能力とは?
自分と物体の位置関係や距離、方向を正しく把握する力のこと。
具体的な場面を挙げると、
- 車の幅や距離感をつかむ
- 駐車のときに「どこでハンドルを切るか」を判断する
- 地図や道順を理解して目的地までたどり着く
- キャッチボールやバドミントンでボールとの距離を測る
- 部屋の片づけで核や収納のバランスを整える
このように、運転や道案内だけではなく、毎日の生活や運動などにも空間認識能力は深く関わっているそうです。
空間認識能力を実感!私のテスト体験
先日、健康診断で「認知症体験テスト」を受けてきました。
テスト内容は大きく3つに分かれていて、
- 計算力&ワーキングメモリのテスト
- ストループテスト(色と文字が違うパターン)
- 空間認識能力テスト
の順で行われました。
1・2は問題なくクリアできたのですが、3の空間認識だけ全然ダメで・・・。
例題から間違えてしまったときは「え!?」と驚いたのを覚えています。
講師の方によると、空間認識能力が低い人は「迷子になりやすい」傾向があるとのこと。
確かに私は昔から方向音痴で、すぐ道に迷ってしまうタイプなので、すごく納得しました。
ここで初めて「私は空間認識能力が苦手なんだな・・・」と実感しました。
空間認識能力が苦手な方の特徴
テストをきっかけに空間認識能力について興味をもち調べてみると、迷子だけではなく、他にもいくつか特徴があることがわかりました。
私自身が特に苦手だと感じたのは、次のようなことです。
- 道に迷いやすい
- 車幅やタイヤの位置がわからず、車の運転が怖い
- キャッチボールなどのボールを使う運動が苦手
- 道案内や地図を説明するのが苦手
- ライブで銀テープが降ってきても取れない
ずっと「不器用だから」「運動神経がないから」と思っていたのですが、空間認識能力も関係しているのかもしれないと気づきました。
もちろん、空間認識能力が苦手な方の特徴はこれだけではありません。
例えば、身近な物の配置を把握しにくい、段取りを考えるのが苦手などといったこともあるそうです。
空間認識能力が苦手だと運転できない?克服する方法はある?
先ほど挙げた空間認識能力の苦手な特徴の中で、私が特に悩んでいるのが「車の運転」です。
免許は持っているのですが、怖いのとテンパってしまって全く運転していなです。
独身の頃は特に気にならなかったものの、
結婚して「子供が生まれたら運転できたほうがいいよね」と考えるように。
そう思いながらも、気づけば7年も経っていました🥲
その間に何度か練習はしたのですが、車幅やタイヤの位置がつかめず、
さらに命などに関わることだと思うと、ますます怖くなってしまったのです。
空間認識能力が関係していた?
「車の運転はできたほうが良い」と頭ではわかっているのに、なぜか上手くできない・・・。
それで、自分を責めてしまっていたこともありました。
でも、先日のテストで「もしかしたら空間認識能力が関係しているかも」と気づいてからは、少し気持ちがラクにったのです。
運転に必要な他の要素と克服の可能性
そこで「空間認識能力が苦手だと運転できないのか?」を調べてみたところ、このようなことがわかりました。
運転には空間認識能力だけではなく、
- 注意力
- 判断力
- 反応速度
- メンタルの強さ
これらも運転に大事な要素だそうです。
つまり、空間認識能力が苦手だからといって、必ずしも運転できないわけではなく、経験や練習でカバーできる部分もたくさんあるそうです。
大切なのは「苦手だから無理」と思い込まずに、少しずつ練習したり、環境を工夫することで前に進んでいける可能性があるのだとわかりました。
 すず
すず私の場合、他の4つの要素も苦手なのですが、少しずつ練習して頑張りたいです( т т )
大人でもできる!空間認識能力を鍛える3つの方法
経験や練習でカバーできるとがわかったので、
「空間認識能力って大人になってからでも鍛えられるのかな?」と調べてみたところ、
- 日常生活
- スポーツ・遊び
- 脳トレ
などを取り入れることで、少しずつ鍛えられることがわかりました。
① 日常生活で簡単にできるトレーニング
- ナビに頼らず地図をみて歩いてみる
- 家具の配置を変えをして新しい空間に慣れてみる
- 料理やお弁当の盛り付けでバランス感覚を意識する
ちょっとした工夫でも「体と頭で空間を意識する習慣を身につける」練習になるみたいです。
実際に私も、昔は駅の乗り換えが苦手で反対方向の乗ってしまうことがありました。でも「今どこにいるのか」を把握するために看板や路線案内を意識して確認するようにしたら、少しずつミスが減っていきました。こうしたちょっとした工夫でも、空間認識を鍛える練習になるんだなと実感しました。
② スポーツや遊びで鍛える
- キャッチボールやバドミントンで距離感を意識する
- ヨガやダンスで身体の位置やバランスを整える
- ボルダリングや立体パズルで立体感を養う
体を動かしながらの練習は、楽しみながら空間認識能力を伸ばせるのはいいですよね🥹💗
遊び感覚で取り入れることで、長く続けられそうです✨
③ 脳トレ
- ジグソーパズルで形や空間を認識する
- テトリスなどの3Dゲームで瞬間的な位置間隔を鍛える
ちなみに私は「数独」が好きで最近の日課にしています。
数独は「空間認識の直接トレーニング」ではありませんでしたが、集中力や記憶力を鍛える効果があるそうです。



空間認識トレーニングと組み合わせると、
脳全体の活性化に繋がるみたいなので、これからも続けていこうと思います🥰
まとめ│空間認識能力との付き合い方
空間認識能力は、運転や道案内などの場面で役立つ能力ですが、苦手だと日常生活で不安になることも多いものです。
私自身も「なんでできないんだろう」と自分を責めてしまったことがありましたが、
「これは空間認識能力の特性かもしればい」と知ったことで、気持ちがふっとラクになったのです。
また、大切なのは、苦手を否定することではなく「そういう自分もいる」と受け入れること。
その上で、
- 日常の小さな工夫
- スポーツや遊び
- 脳トレ
などを取り入れていけば、少しずつ改善やカバーができることがわかりました。



空間認識能力が苦手でも、大丈夫。小さな工夫を重ねながら少しずつ前へ進んでいけたらと思いました。
最後まで読んで頂きありがとうございました🌷
少しでも参考になれれば嬉しいです!
もし、この記事を気に入っていただけたら、
他の「貯め体質になる暮らし」の記事もぜひ、のぞいてもらえたら嬉しいです👀✨
もし何かありましたら、
コメントやお問い合わせまでお気軽にどうぞ🌸
今日も家計管理、おつかれさまでした🌿✨

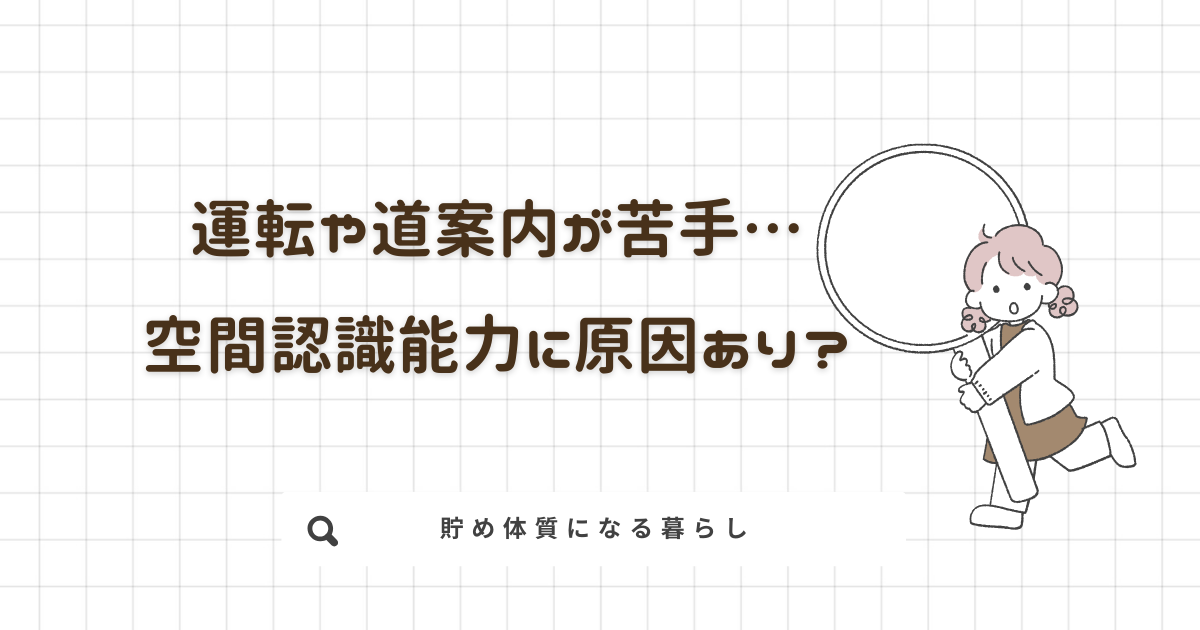
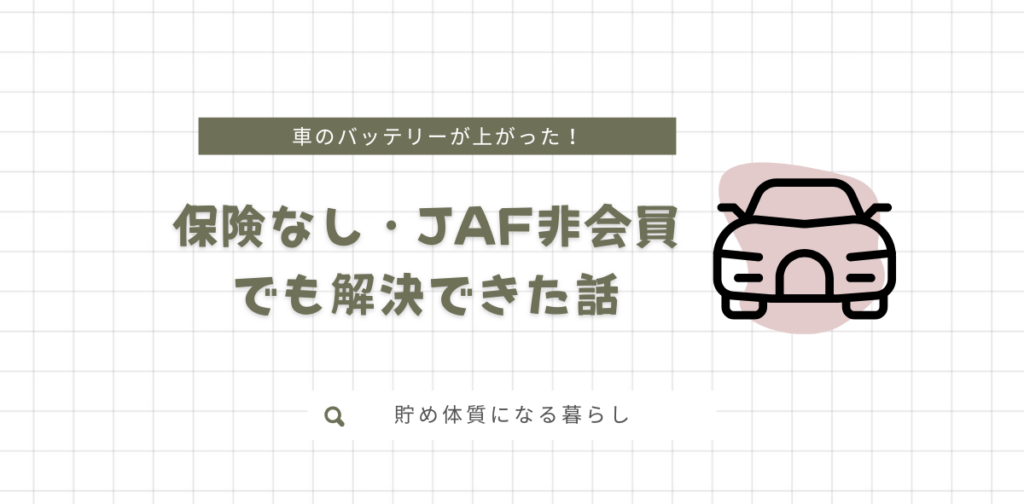




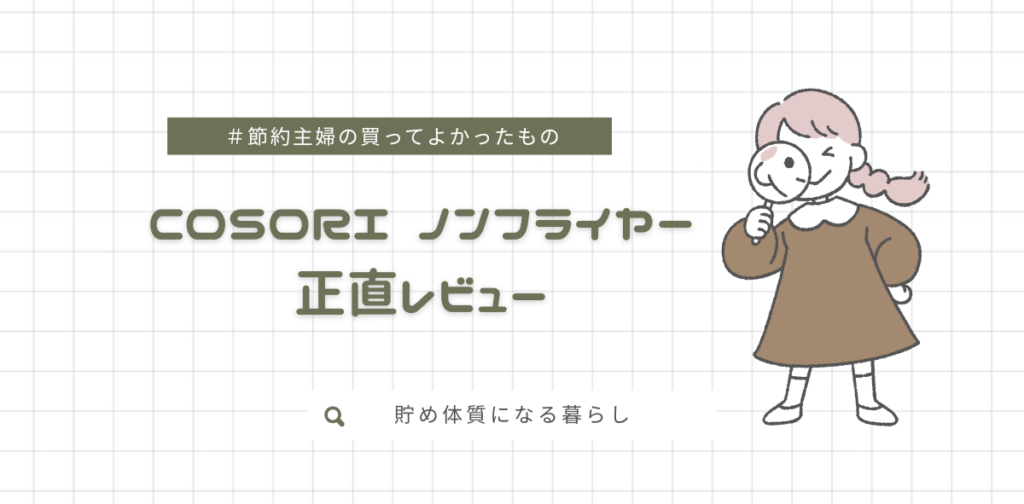
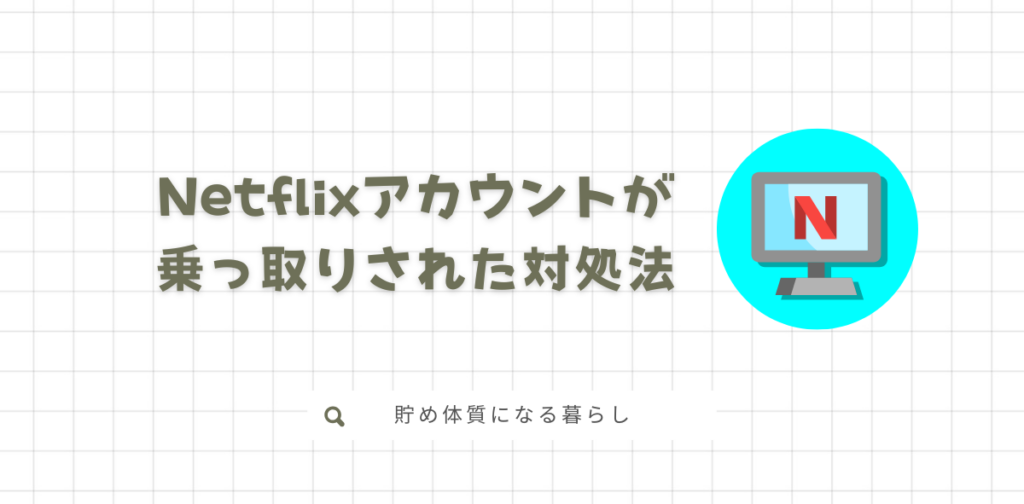




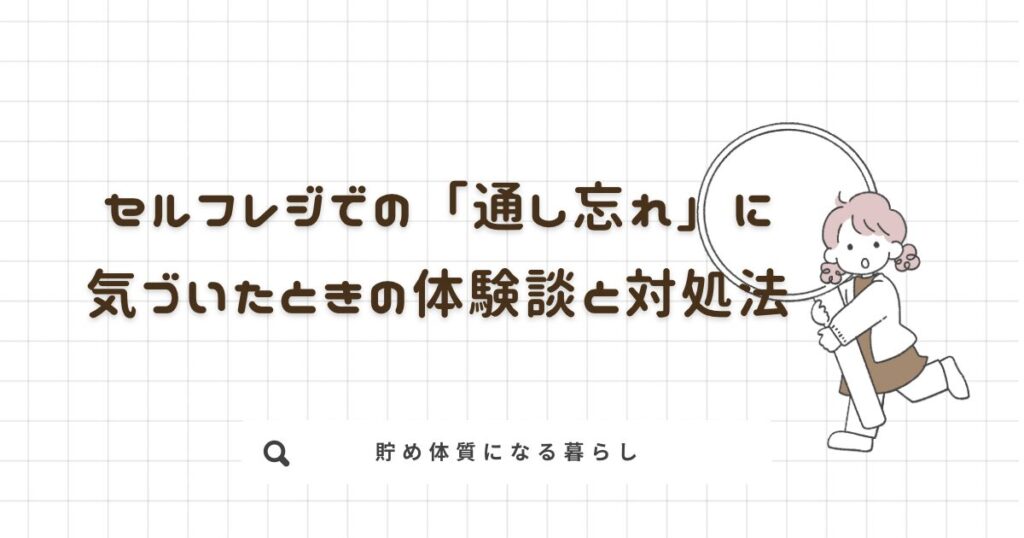
コメント